

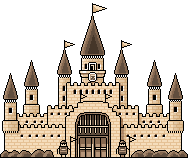
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
大雪の鳥取から、更に雪深い山形に移動・・・。 (とにかく寒かった) 大雪の中、○○先生の運転で山寺まで連れていっていただきました。 山寺は、正しくは宝珠山立石寺といい、 貞観2年(860)清和天皇の勅願のよって慈覚大師が開いた、天台宗のお山。 正面の大きな建物は、国指定重要文化財の根元中堂である。 延文元年(1356)初代山形城主・斯波兼頼が再建した、入母屋造・5間4面の建物で、 ブナ材の建築物では日本最古といわれ、天台宗仏教道場の形式がよく保存されている。 堂内には、慈覚大師作と伝える木造薬師如来坐像が安置され、 伝教大師が比叡山に灯した灯を立石寺に分けたものを、 織田信長の焼打で延暦寺を再建したときには逆に立石寺から分けたという、 不滅の法灯を拝することができる。 次に、そば処 三百坊に板蕎麦を食べにGO! 三百坊の謂われ : かつて、西暦852年頃、この地には、瀧山霊山寺という中心となる修験場があり、 その隆盛時には、300を数えるほどの多くの坊舎が、立ち並んで、いかにも壮観であったという。 やがて、あまりに大きくなりすぎてしまった勢力を削ぐため、 鎌倉幕府により、閉山を余儀なくされ、跡形もなくなってしまって、今日に至る。 なお、店名は、その当時、この場所を、三百坊と呼び慣わしたことに因っている。 この地に、山形の庄屋・陣屋であったという大きな建物を、 1972年に移築。蕎麦屋としての商いは、今年で、23年目に入るそうです。 ※冬の山形は、大雪で大変でした。 ○○先生、いろいろ案内していただき有難うございました。 |
|
 山寺(宝珠山立石寺) 根本中堂 |
山寺とは愛称であり、実際は 『宝珠山立石寺』というのが正式名。 平安時代前期、第56代清和天皇の命により、 比叡山・天台宗の高僧の慈覚大師 により開山された霊場。  御神木 |
 芭蕉像 |
松尾芭蕉が『奥の細道』で 「閑さや岩にしみ入る蝉の声」 という俳句を詠んだ有名な名所でもある。  雪に埋もれた句碑 |
 そば処 三百坊 |
関が原の戦い(1600年)から存在していた小林家 を1972年に移設した建物 山形の小正月の伝統「だんご木」 が大黒柱に飾られていました。  だんご木飾り |
 三百坊 の庭園 |
通常の板そばメニューに対して、 こちらの”坊板そば(十一そば)”は、 蕎麦の産地である=地元 西蔵王産、 敷地内の畑にて自家栽培されている。  坊板そば (自家栽培の一番、二番蕎麦粉を使った十一そば) |